(2025.08.22)「福井女子中学生殺人事件」再審無罪判決に関する会長声明
1 2025年7月18日、名古屋高等裁判所金沢支部(増田啓祐裁判長)は、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」(以下「本件」という。)について、前川彰司氏(以下「前川氏」という。)に対し、再審無罪判決を言い渡した(下記の福井地方裁判所が言い渡した無罪判決に対する検察官の控訴を棄却する判決。以下「本判決」という。)。
2 本件は、1986年3月19日に、福井市内で女子中学生が殺害された事件である。前川氏は、犯人であることを裏付ける明らかな物的証拠がなく、かつ犯行を直接目撃した人物がいなかった中で、関係者の供述に基づき事件発生の約1年後に逮捕され、起訴された。これに対して前川氏は、当初から一貫して無罪を主張してきた。
3 1990年9月26日、第一審(福井地方裁判所)は、検察官が前川氏の犯人性を基礎付けると主張した関係者らの供述について、重要な点で変遷があることや客観的な裏付けに乏しいこと等からその信用性を否定し、無罪判決を言い渡した。ところが、これに対して検察官が控訴したところ、控訴審(名古屋高等裁判所金沢支部)は、関係者らの供述が「大筋で一致」するとしてその信用性を認め、1995年2月9日、前川氏に有罪判決(懲役7年)を言い渡した。前川氏は最高裁判所に上告等をするも、同裁判所はこれを退けたことから、上記有罪判決が確定した(以上、確定審)。
4 2004年7月、前川氏は刑期を終え、確定した有罪判決を言い渡した名古屋高等裁判所金沢支部に対し、第一次再審請求を申し立てた。再審請求審(同支部)では、関係者らの供述調書の一部など95点の証拠が開示された。その結果、関係者らの供述の変遷がいっそう明らかになったところ、2011年11月30日、名古屋高等裁判所金沢支部は、関係者らの供述の信用性を否定し、再審開始決定を言い渡した。ところが、検察官から異議申立てがされ、再審異議審(名古屋高等裁判所)は、2013年3月6日、再審開始決定を取り消した。この判断は特別抗告審(最高裁判所)でも維持された。
5 2022年10月14日、前川氏は第二次再審請求を申し立てた。再審請求審(名古屋高等裁判所金沢支部)では、裁判所の積極的な訴訟指揮もあり、検察官より新たな証拠287点が開示され、一部の関係者の証人尋問も実現された。その結果、2024年10月23日、名古屋高等裁判所金沢支部は、関係者の一人が自己の利益を図るために前川氏を犯人とする虚偽供述を行い、捜査機関が他の関係者に誘導等の不当な働きかけを行って関係者らの供述が形成されていったという具体的かつ合理的な疑いがあるとして、関係者らの供述の信用性を改めて否定し、再審開始決定がなされた。その後、検察官が異議申立てを断念し、この再審開始決定が確定した。
6 2025年3月6日、名古屋高等裁判所金沢支部にて第1回再審公判が開かれた。第二次再審請求審までに提出された証拠以外に証拠の請求はなく、検察官の有罪の論告と弁護人の無罪の弁論が行われ、即日結審した。
2025年7月18日の判決(以下「本判決」という。)は、関係者供述の信用性を否定し、前川氏に対する第一審の無罪判決を維持し、検察官の控訴を棄却した。
同判決の中では、関係者の一人が本件に関する前川氏の犯人性を基礎づける情報の提供と引き換えに、自らが勾留されていた別件の刑事裁判における刑の軽減などの利益を図ろうとする態度を示し、供述の変遷も大きかったにもかかわらず、捜査を行った警察官らが、不当な利益を供与する(勾留中に本来差入れが認められない食料品(寿司)の差入れを認める、同人の希望に応じて警察署から刑務所への移監を一時取りやめる、同移監後には希望に応じて警察署に再度移監する)などして同人の不正な意図を助長させたばかりか、同人と他の関係者らとを直接面会させて本件について話をさせたりするなどしていたことを認定し、他の関係者らの「供述を汚染させる結果となった可能性が否定できない」とした。
また、捜査を行った警察官の一人が、私的な交際関係のない、重要証人であった関係者の一人に、証人尋問に近い時期に結婚祝の金銭を交付したと認定し、職務の公正を保つべき警察官がこのようなことをすること自体が、「犯罪行為とはいえないにしても、公正であるべき警察官の職務に対する国民の信頼を裏切る不当な所為」であるとした。
さらに、本判決は、確定審を担当していた検察官(以下「確定審検察官」という。)は、主要関係者の供述の信用性を判断するにあたって重要な前提事実について誤りがあることを把握していたにもかかわらず、これを秘するだけでなく、その誤った事実を第一審の論告以降も「ぬけぬけと主張し続け」ていたと認定した。このような検察官の訴訟活動について、本判決は、「裁判所に法の正当な適用を請求し、公益を代表する検察官としてあるまじき、不誠実で罪深い不正の所為といわざるを得ず、適正手続確保の観点からして、到底容認することができない。」、確定審検察官がこの誤りを適正に是正していれば、そもそも再審請求以前に確定審において第一審の「無罪判決が確定していた可能性も十分に考えられるのであって、上記のような確定審検察官の訴訟活動に対しては、その公益の代表者としての職責に照らし、率直に言って失望を禁じ得ない。以上のような検察、警察の不正、不当な活動ないしその具体的な疑いは、単に検察、警察に対する信用を失わせるのみならず、刑事司法全体に対する信頼を揺るがせかねない深刻なものである。」と判示した。
本判決は、2025年8月1日、検察官が上訴権を放棄する手続をとったことで確定した。
7 本判決は、前川氏の無罪を改めて明らかとするものであって、当会として高く評価する。
他方で、確定審以来、上記で判示されたような、重要な前提事実に誤りがあることを知りながらそれを秘して訴訟活動を行い、また、証拠開示について消極的な姿勢をとり、事案の解明及びえん罪被害の救済を阻んできた検察官の態度は、公益の代表者としてあるまじきものであることはいうまでもない。また、本判決の指摘するとおり、主要関係者に不当な利益を供与し、その不正な意図を助長させたり、重要証人であった関係者に、私的交際関係がないにもかかわらず金銭を交付したりした警察官の行為は、公正であるべき職務に対する国民の信頼を裏切る不当な所為である。
当会は、検察や警察に対し、本件に関して真摯な反省をするのみならず、前川氏に謝罪すること、本件を検証して再発防止策を検討し、公にすることを強く求める。
8 本件には、いわゆる「袴田事件」と同様、現在の再審法の不備が顕著に表れている。本件では、捜査機関が不正、不当な捜査活動や訴訟活動(その具体的な疑いがあるものを含む。)を行い、そこには「少なくとも確定審検察官において不利益な事実を隠そうとする不公正な意図があったことを推認されても仕方がない」ものが含まれていた。そのため、これを明らかにした再審請求審における証拠開示が、事案の解明に決定的に重要な役割を果たしており、これがいかに重要であるかが改めて認識された。
加えて、前川氏が最初の再審開始決定を受けてから再審公判を受けるまでに13年以上の月日を要した点には、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが認められていることの弊害が表れている。
当会は、「福井女子中学生殺人事件」の再審無罪判決を受けて、政府及び国会に対し、改めて、再審請求手続における全面的証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止及び再審請求審における手続規定の整備を含む再審法の速やかな改正を強く求める。
以上
2025年(令和7年)8月22日
岡山弁護士会
会長 土 居 幸 徳

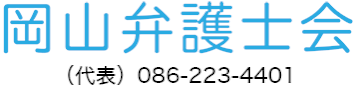
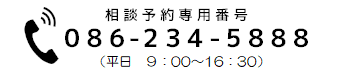
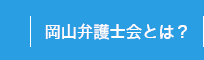
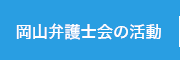
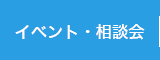
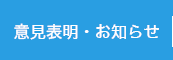
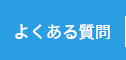
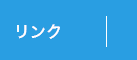
 岡山弁護士会
岡山弁護士会

