(2025.08.22)2025年秋臨時国会における選択的夫婦別姓の法制化を求める会長声明
1 夫婦同姓にかかる問題の所在と経緯
民法第750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と定めている。その結果、女性である妻が夫の姓を名乗る割合が約95%に上るという性別による著しい不平等が生じ、「法の下の平等」を保障した憲法第14条、並びに「夫婦が同等の権利を有することを基本とし」、婚姻に関しても「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と規定した憲法第24条第1項及び第2項に反する状況が長年にわたり続いている。また、氏名は憲法第13条により保障される人格権の重要な一内容であるところ、婚姻に際して改姓したくない者に改姓を強制することは、その人格権を侵害するものである。さらに、夫婦が同姓にならなければ婚姻できないことにより、同様に憲法第13条により自己決定権として保障される婚姻の自由が不当に制限されている。
このように法律で夫婦同姓を義務付けている国は、日本のほかには見当たらず、日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、20年以上の間、再三にわたり、夫婦同姓を義務付け、多くの女性に夫の姓を採用することを強いている民法の規定を見直し、選択的夫婦別姓を導入するよう勧告を受けている。
婚姻時に選択的夫婦別姓を認めない民法及び戸籍法の規定の違憲性を争う、いわゆる選択的夫婦別姓訴訟も第3次訴訟に及び、当事者の原告らは別姓を選択できない精神的苦痛、同姓を義務付けられることによる自己喪失感を訴え続けている。
官民の近時の世論調査の結果では、選択的夫婦別姓の導入に賛成する意見が高い割合となり、多くの地方議会でも同制度の導入を求める意見書が採択され、日本経済団体連合会も、2024年6月18日、選択的夫婦別姓制度の早期実現を求める政府への提言を公表している。
日本弁護士連合会も、2024年6月14日開催された定期総会において、「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」を採択している。
2 2025年通常国会における法案提出
以上のような経緯のもと、2025年1月24日召集された通常国会の終盤において、ようやく立憲民主党、国民民主党、日本維新の会の各党から選択的夫婦別姓制度に関する法案が提出された。これにより、1997年旧民主党が法案を提出して以来、実に28年ぶりに、国会で審議が開始され、参考人質問が行われた。
このように、選択的夫婦別姓法案が提出され、審議入りしたことは極めて意義深いが、3法案の上記国会での採決は見送られ、2025年秋の臨時国会で継続審議とすることに与野党で合意された。
3 選択的夫婦別姓法案に対する意見
上記国会に立憲民主党が提出した法案及び国民民主党が提出した法案は、いずれも1996年の法制審議会の案がベースとなっており、婚姻時、同姓、別姓のいずれかを強制することなく、改姓するかどうかを自ら決定する選択の自由を認め、多様な生き方を尊重し、選択肢を広げるものであり、大多数の妻が夫の姓を名乗り、性別による著しい不平等が生じ、法の下の平等(憲法第14条)及び個人の尊厳と両性の本質的平等(憲法第24条)に反している状況を解消することにつながるものである。
これに対しては、子の姓と両親の一方の姓が異なることにより家族の一体感が損なわれる、子の福祉に悪影響があるなどの意見があるが、現在、事実婚を選択し、子と両親の一方との姓が異なる家族において、家族の一体感が損なわれる、子の福祉に悪影響が及んでいるとの声は聞かれない。令和4年3月内閣府政府広報室の「家族の法制に関する世論調査」の報告によれば、令和3年12月の世論調査の結果、夫婦・親子の名字・姓が違うことにより、家族の一体感・きずなには影響がないと思うと回答した人の方が多く、しかも若い世代ほど多くなっている(https://survey.gov-online.go.jp/r03/r03-kazoku/2-2.html)。
また、別姓制度を導入している圧倒的多数の国において、同制度のために家族が崩壊しているという事実も認められない。
上記両法案は、婚姻時に将来出生する子の氏を決めておくという内容であり、出生後に両親の意見の相違で子の氏が決まらないという事態を回避し、子の氏の統一を原則とすることで、子の利益についても配慮されているうえ、事情により家庭裁判所の許可を得て子の氏を変更する道も残されている。
さらに、上記法案では、戸籍制度は維持され、戸籍システムの変更及びそれに要するコストもわずかであるし、企業の顧客管理システムあるいは労務管理システムに及ぼす影響も少ない。
4 通称使用法案に対する意見
一方、日本維新の会が提出した法案は、旧姓の通称使用を法制化しようとするもので、一部の世論調査の結果ではこれに賛同する意見も見られる。
しかし、前述の内閣府政府広報室の「家族の法制に関する世論調査」の報告によれば、婚姻による名字・姓の変更により何らかの不便・不利益があると思うと回答した人が何らの不便・不利益もないと思うと回答した人を上回っており、さらに、不便・不利益があると思うと回答した人の約60%が通称使用だけでは対処しきれない不便・不利益があると思うと回答している。
現在でも旧姓の通称使用はある程度認められているところ、多くの女性が戸籍上の改姓によりアイデンティティの喪失に精神的苦痛を感じたり、キャリアの断絶で人格的利益が侵害されたりしている。また、金融機関での預貯金等口座開設時や海外ビジネス上の煩雑さといった不都合もあり、通称を使用しようとする者とそうでない者との間には著しい不平等が存する。海外では、パスポートのICに掲載されていない旧姓の併記により偽造が疑われ、混乱が生じているとの報告もある。このような人権上、社会生活上の数々の問題は通称の法制化によっても解消されるものではない。
さらに、通称使用を法制化する場合、極めて多数に及ぶ関係法令及び戸籍システムの大幅な変更が必要となり、多大な労力と費用を要するうえ、金融機関等の顧客管理システムの変更及びマネーロンダリング対策並びに企業の労務管理等のシステム変更に要する人的・経済的コストも甚大となる。
このような問題が十分に周知されないまま行われた世論調査の結果をもとに通称使用の法制化を進めるのは相当でない。
5 選択的夫婦別姓の法制化に対する社会の要請
婚姻による改姓や通称使用による精神的苦痛から離婚し、事実婚となっている夫婦も、法律婚に復することを希望し、夫婦別姓制度の早期導入を求めている。
若い世代の中には、男女ともに婚姻後も婚姻前の姓を使い続けることを希望し、選択的夫婦別姓に法改正されるまで婚姻や妊娠を先延ばしにしている人もいる。
現に、内閣府男女共同参画局作成の男女共同参画白書令和4年版によると、積極的に結婚したいと思わない理由として「名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」と回答した人は、20 ~30代で 女性25.6 %、男性11.1%、40~60代で女性35.3%、男性6.6%であり、男女ともに一定数いることが明らかになっており、しかも改姓することの多い女性の方が男性より相当高い割合となっている。
また、ジェンダー平等社会の実現を目指して活動する一般社団法人「あすには」の2025年3月の調査の結果、事実婚をしている20~50代で選択的夫婦別姓待ちの結婚待機人数は58.7万人にも上ると算定されている。早期に選択的夫婦別姓制度を導入することは、社会的要請でもある。
6 結論
岡山弁護士会は、2016年1月、2021年4月、2021年7月、2025年3月と4度にわたり、選択的夫婦別姓の法制化を求める会長声明を発出してきたところであるが、今もう一度、2025年秋の臨時国会において選択的夫婦別姓の法制化を実現するよう強く求める。
以上
2025年(令和7年)8月22日
岡山弁護士会
会長 土 居 幸 徳

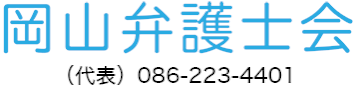
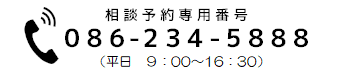
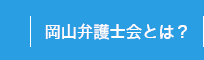
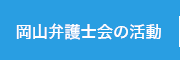
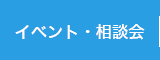
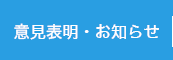
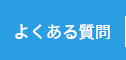
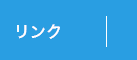
 岡山弁護士会
岡山弁護士会

