(2025.09.11)臨時国会での再審法改正の実現を求める会長声明
1 2025年6月18日、衆議院に「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)が提出された。本法案はその後、衆議院法務委員会に付託され、閉会中審査となっている。
本法案は、「再審制度によって冤(えん)罪の被害者を適正かつ迅速に救済し、その基本的人権の保障を全うする」という観点から、①再審請求審における検察官保管証拠等の開示命令、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、③再審請求審等における裁判官の除斥及び忌避、④再審請求審における手続規定を定めるものである。
これは、当会の2023年12月21日付け総会における再審法の改正を求める決議の内容と軌を一にし、当会として高く評価する。
また、当会は、2024年3月の発足以来、精力的な活動を行って本法案を結実させた、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」(以下「再審法改正議連」という。)及び関係者各位の尽力に対し、深い敬意を表する。
2 再審法改正は、上記本法案の提出理由のとおり、えん罪被害者を適正かつ迅速に救済するものでなければならない。そして、上記4項目は、えん罪被害者の適正かつ迅速な救済を実現するために特に重要なものである。
実際、近時再審無罪判決が確定した、袴田事件や福井女子中学生殺人事件においては、捜査機関によるねつ造や、確定審において捜査機関側の手持ち証拠(弁護側へ未開示)に反する主張が検察官からされていたこと等が認定されている。このような認定にあたっては、裁判所の指揮による証拠開示が重要な役割を果たしている。これらのことは、①再審請求審における検察官保管証拠等の開示命令は必要不可欠であることを裏付けている。
次に、再審開始決定に対し、検察官に不服申立てが認められていることで、再審開始決定の確定までが長期化してしまっている(1回目の再審開始決定から、その確定まで、袴田事件で約9年、福井女子中学生殺人事件で約13年が経過している。)。再審開始決定確定後には再審公判があり、再審公判では検察官の不服申立てが認められていることに鑑みれば、②再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止もまた必要不可欠である。
③過去の審理に関与した裁判官がその事件の再審の手続に関与できなくなることは、公平・公正な裁判を受けるため当然であることはいうまでもない。
最後に、第1次再審請求申立てから再審開始決定確定まで、袴田事件で約42年、福井女子中学生殺人事件で約20年が費やされているところ、これは再審手続を審理する期日の指定や手続の進行方法に関して明確な定めがなく裁判所の広範な裁量に委ねられていることも影響しているため、申立て後早期に再審請求手続期日を開くことを義務付ける規定といった④再審請求審における手続規定を定めることはやはり必要不可欠である。
このとおり、これらの4項目については必要不可欠ないし当然認められるべき内容であるところ、早急に法改正がなされる必要がある。
3 これに対し、これまで再審法改正に消極的な態度をとってきた法務省が、再審制度の見直しを法制審議会に諮問し、2025年4月21日以降、同審議会の刑事法(再審関係)部会(以下「法制審部会」という。)において、本法案の定める上記4項目も審議されている。
しかし、再審に関係する一方当事者の検察と密接不可分の関係にある法務省が事務局を務める法制審議会が、再審法改正を主導することには、強い懸念がある。実際、再審手続における証拠開示の範囲を新証拠及びそれに基づく主張に関連する限度にとどめようとする意見や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することに消極的な意見も法制審議会にはみられるところである。
また、このような様々な意見を受けて、事務局を務める法務省が原案を取りまとめる形で、上記4項目の改正に関する是非を含む全14項目という多くの論点が提示されている。これでは、その法制化までは相当な期間を要してしまうことが明らかである。
このような法制審部会の結論を漫然と待つことは、本法案の提出理由にもされている、冤(えん)罪の被害者の「適正」、「迅速」な救済のいずれの観点からも難があるといわざるを得ない。
4 以上に鑑みれば、まずは国会において、早期に議員立法たる上記4項目を内容とする本法案を可決・成立させ、あるべき再審法改正の方向性を示すことが重要である。そのうえで、法制審議会ではこの議員立法の方向性に沿って審議を尽くした上、更なる改正が行われるべきである。
5 よって、当会は、国会に対し、速やかに本法案の審議を進め、今秋に予定されている臨時国会において、議員立法たる本法案を可決・成立させることを強く求める。
以上
2025年(令和7年)9月11日
岡山弁護士会
会長 土 居 幸 徳

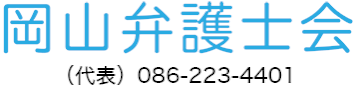
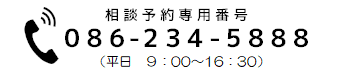
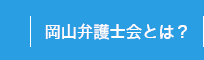
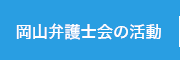
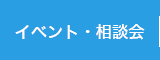
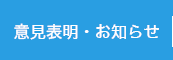
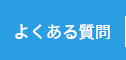
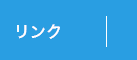
 岡山弁護士会
岡山弁護士会

